皆さんおはようございます✨ドリ丸です🎉
またこいつと対面する日がやって来てしまいました😡

シアノバクテリアです🥶
茶コケ、緑コケ、ひげコケ、海水水槽には様々なコケが発生するものですが、これらのコケはどうとでもなります。
しかし❗
シアノバクテリアだけはダメです❌
赤褐色のベタっとした見た目も非常に気色悪いシアノバクテリアがライブロックの隙間や水槽裏に繁殖していたのでした。
シアノバクテリアとは?(ウィキペディア調べ)
~シアノバクテリア(cyanobacteria,藍藻(もしくはラン藻)とも呼ばれます)は、酸素を発生する光合成(酸素発生型光合成)を行う原核生物です。酸素発生型光合成は、植物の光合成と基本的に同じものです。シアノバクテリアの祖先は30~25億年前に地球上に出現し、初めて酸素発生型光合成を始めました。この光合成では水を電子供与体とする(水分子から電子を奪い、その副産物として酸素ができます。)ことができるため、水と光があればエネルギーが得られることとなり、当時の地球上で大繁殖したようです。その結果、それまでの酸素を含まない嫌気的な大気に酸素を供給することとなり、徐々に(実際には酸素レベルが急上昇した時期もありましたが)現在に近い酸素を豊富に含む好気的大気に変えていったと考えられています。シアノバクテリアは、進化の過程で、形態的にも代謝的にもきわめて多彩な能力を有する原核生物の大きな一グループを形成するようになったようです。また、真核細胞の祖先との内部共生によって真核細胞に取り込まれ、植物の葉緑体の祖先となったと考えられており、原核生物から植物に至る光合成の進化を考える上で、非常に重要な生物です。 形態的に、大まかには単細胞性と糸状性に分けられ、糸状性の種には細胞分化の能力を有するものがあります。また、窒素固定を行う能力を有する種と有さない種、完全暗所でもグルコースなどを使って従属栄養的に生育できる能力がある種と光合成的な生育しかできない種など、代謝能力は多様です。また、代謝能力と細胞の形態とは必ずしも一致しません~
難しい事がつらつら書かれていましたが、なぜシアノバクテリアがダメかと言えば、この細菌バクテリアはほっておけば水槽内で大繁殖し、サンゴも覆い尽くし全滅させてしまうのです😭
では今回なぜシアノバクテリアが発生してしまったのか?
シアノバクテリアの発生要因は様々ありますが、この水槽で言える事は、サンゴ過密水槽にしている事からなる水の淀みが原因と思われます。

2台の水流ポンプで水を回していましたが、水槽下部やライブロックの隙間の隅々まで水がしっかり回りきれなかったのでしょう😥
このまま放置していては水槽をリセットしなければならなくなる為、ドリ丸が取り寄せた生体が…
【タツナミガイ】でした❗
シアノバクテリアが発生した場合の対応策
海水水槽を長年やっている方であれば、シアノバクテリアの経験は1度や2度はある事でしょう。多くのアクアリストの方が、独自の経験体験を元に対応されていますが、信憑性の高い対応策は4つです(あくまでも個人的意見ですがね)
当然の事ながら水質改善、照明の改善はした上での対策方法です。
①物理的除去
水替え時にプロホースで吸い出してしまう方法です🤗これは「底砂にシアノバクテリアが発生している」場合に良く用いられる方法で、シアノバクテリア初期段階であればこれでいけます。
②機材による除去
水の淀み、また止水域にシアノバクテリアは発生しやすいので、その部分に水流ポンプを増設します。小型て薄くパワーのある水流ポンプがこういう場所には最適ですから【ミニットストリーム2000】は最適な水流ポンプと言えます。
以前はこれ付けていたんですが、故障した為取り外してしまったんですよね。また購入するかもしれませんね😅
小型水槽から大型水槽まで使える「ミニットストリーム2000」とは?
③薬品除去
「もう大繁殖させてしまって手をつけられない。リセットするしかないかなぁ」そこまで大変な状況になってしまっているのであれば「アンチレッド」という薬品があります。
規定量を守り毎日添加していく事で、ベッタリとライブロックに張り付いていたシアノバクテリアが次第に岩から剥がれるように落ちていきます。
サンゴや海水魚に影響はないの?🤔
メーカー発表では無害とされていますが、この薬品を使った事で海水魚が☆になったり、サンゴが開かなくなったというレビューがあるのも事実。
でも間違いなくシアノバクテリアは全滅できる商品です👌
④生物による除去

さぁお待たせ致しました。いよいよ「タツナミガイ」の登場です❗👏 🤗👏
水槽内のコケはコケを食べる生体を入れるのが、アクアリウムでは一般常識ですよね。シッタカガイ、マガキガイ、ハギなんかは当然の事ながら水槽に入っているでしょう
しか~し❗
シアノバクテリアはこれらの生物は食べないんです❌毒とわかっているからマガキガイもシアノバクテリアは避けて通ります。
唯一食べてくれる生物がタツナミガイなんです。
でも誤解しないで下さいね。タツナミガイがシアノバクテリアを好んで食べるかと言えばそうではなく、シアノバクテリアも食べれると言った表現が正しいでしょう(実際、シアノバクテリアばかり食べさせると弱ります)
別名「コケモンスター」と呼ばれる程、タツナミガイは水槽内のありとあらゆるコケを食べ尽くしてくれる、ある意味最強のコケ取り生体なのです。
でもですねぇ、このタツナミガイ中々ショップにいないんです😅入荷量も少ないし、入荷した途端売れてしまうらしいですから。
全国のアクアショップに電話しまくってようやく一匹だけ見つけ出した次第です😍
タツナミガイの特徴、及び飼育の仕方について
①タツナミガイとは?

見た目は見ての通り美しいものではありません😅ぶさ可愛い⁉️生き物です🤩
海でアメフラシを見た事はありますか?タツナミガイは、「貝」ではなくアメフラシ科に属する軟体動物です。刺激を受けると背中から紫色の液体を出します(無害)昔々は貝も付いていたようで、退化した薄い板状の貝が体内に存在します。
学名ではなく英名でWedge Sea Hareと呼ばれ、日本語に訳すと「くさび形をした海のウサギ」との事らしいのですがウサギに見えるかと言えば微妙です。
①学名は?
Dolabella auricularia
②何を食べるの?
茶コケ、緑コケ、海藻、そしてシアノバクテリア。コケ取りモンスターと呼ばれる程、水槽内のコケを食べ尽くしてくれるホントにありがたい生き物です🤣
夜行性の為、昼間は砂の上でじっとしてるか、ライブロックの隙間でじっとしています。照明が消えるとモリモリとコケを食べ出しますよ。
先程も言いましたがシアノバクテリアを食べてくれる生物はタツナミガイ位です。ターボスネイルも食べると聞いた事はありますが、実際そこまでの変化は感じませんでしたね。
ただし、食べるコケがなくなってしまうと餓死してしまいますから中々長期飼育は難しいタツナミガイです。
長期飼育をされるのであれば別水槽を準備し、海藻等を与えてあげる必要があります。
③水温は何度飼育?
16℃~25℃です🤗現実的に考えてサンゴや海水魚が入った水槽に入れられるでしょうから22℃~25℃の水温で育てる事になるでしょう。
タツナミガイは低水温には強く、高水温にはめっぽう弱い事は知っておいて下さい。
死なせてしまうと水を極端に汚し、すごい異臭を放ちますから水槽用クーラーの夏場の設定温度は24℃をお勧めします。
④海水魚との混泳は大丈夫?
基本的には大丈夫です🤗ただ、気性の荒い海水魚や、フグやモンガラのような興味本位で突つつくような海水魚と混泳させると、常に紫色の体液を出している可能性はありますね。
⑤サンゴ水槽でレイアウトは壊されない?
注意が必要です❗タツナミガイはサンゴを食べたりはしません。
では何に注意かと言うと大きさです。10センチ以上のサイズになると、その体格から接着されてないサンゴは落とされてしまう可能性が高いのです。
逆に5センチ未満のサイズでしたら、サンゴとサンゴの隙間をナメクジの様に器用にすり抜けて動き回ります。特にサンゴ過密水槽の場合、そこにはデトリタスも溜まりやすいので、クリーナーとして大活躍してくれます。
タツナミガイを入れるのであればサンゴは接着剤で固定されておかれた方が安心です。
⑥どれくらい大きくなるの?
25センチ程です🤗長期飼育された場合かなり大きくなります。しかしながら水槽環境下では10センチ前後が主な大きさです。
⑦寿命はどれくらい?
水槽環境下での最長寿命記録は6年です。基本的には1~3年と言われていますが、コケがなくなると途端に餓死しますから数週間、数ヶ月で☆にという方が多いのも事実です。
「コケを減らすため」「シアノバクテリアをなくす為」と割りきって入れられる方がほとんどです。
⑧注意点は?
毎日死んでないかのチェックです。アメフラシ系は水槽内で☆になると、ものすごく水を汚しますから、すぐに取り出さなければいけません。
「コケがだいぶ無くなり水槽が綺麗になったなぁ」
それはまもなくタツナミガイが餓死する時が来たという事です。
タツナミガイ水槽投入
①水温合わせ

袋のまま約20分程浮かべていたら完了です。
②水質合わせ

マガキガイやシッタカガイでしたらいきなり水槽にドボンしても大丈夫ですが、タツナミガイはしっかり水質合わせをされた方が安心です。
点滴法で約1時間程水質合わせを行いました。冬場であればヒーターを、夏場であれば部屋のクーラーで水温を23℃前後を保つようにしてあげて下さい。
③水槽投入

さっそくシアノバクテリアが繁殖している場所に投入しました。
じっとしていましたね。
さぁこちらのタツナミガイは本当にシアノバクテリアを食べてくれるのでしょうか。
投入前のシアノバクテリアの様子

水槽投入直後のシアノバクテリアに向き合うタツナミガイ

モリモリとシアノバクテリアを食べる様子


投入後(1週間)シアノバクテリアの様子

お見事です❗この部分のシアノバクテリアは殆ど食べてくれました❗
まだまだ隙間部分には残っていますから、この調子で食べ尽くしてくれる事でしょう🤩
④飼育してみてわかった事

このタツナミガイ、茶コケや柔らかい緑コケが大好物のようです。ガラス面にうっすら付いた茶コケは、シッタカガイと競い合う位の勢いで食べていきます。
ただですねぇ、ガラス面にタツナミガイが張り付いているのは中々の存在感ですよ。まだ現在は8センチ程の大きさですが、これが倍の15センチとかになると見た目的にも「う~ん」となるかもしれませんね😅
⑤実際にどれくらい生きたか?
約2ヶ月で居なくなりました。しかも水槽のどこ探してもその姿は見えないのです。最初は「岩影にでも隠れているのかなぁ」と思っていたのですが、全く姿を見ない日が続き★になったと諦めました。
タツナミガイのおかげで水槽内のありとあらゆる苔は食べ尽くされキレイにはなったのですが、大量の苔を必要とするタツナミガイにとってこの様な状況になるとやっぱりダメでしたね。
しかも死んだらすぐに取り出さないといけません❗と言っておきながら、ドリ丸は見つけることさえ出来ませんでしたので取り出せてません。
だからといって魚には影響が出ず、タツナミガイが★になった水槽でも大丈夫でしたよ。
ただし、やはり大量の水替えは行いましたけどね。
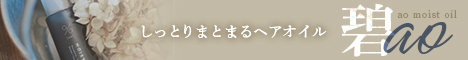
まとめ
シアノバクテリア発生の為、今回初めてタツナミガイを投入したのですが、予想をはるかに上回る程、水槽内のあらゆる場所のコケを食べてくれます👌
シアノバクテリアもそうですが、茶コケ、緑コケもどんどんなくなっていってます🤗
シアノバクテリアをタツナミガイは本当に食べてくれるのか❔という検証は、間違いなく食べてくれますが正解です。
【買って良かったアクアリウム機材】


